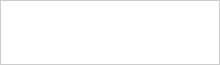矯正治療
歯並びを悪くしていた原因は良くない呼吸だったんです!
お子さんは、大きないびきをかいていませんか?
夜中に息をこらえたりしていませんか?
鼻づまりで口を開けて息をしていませんか?
たびたびカゼをひいたりしていませんか?
昼間にとても眠そうにしていませんか?
集中力が不足していると感じたことはありませんか?
朝起きてぐずったり、疲れたりしていませんか?
猫背ではありませんか?
頬杖をついていませんか?
中耳炎やアレルギー症状が出やすくありませんか?
もしかするとこれらの症状はお子さんの呼吸の問題が原因かもしれません。そういうお子さんがとても増えています。
そしてその呼吸の問題が歯並びの問題の原因だったのです!
前歯が乱れている子も、受け口の子も、出っ歯の子も、上下前歯がかみ合っていない子も、みーんな、呼吸に問題があったのです!
そして小さい頃にその点を歯科矯正治療で改善することがそのような子たちにとってとても大切だったんです!!
(ちなみに大人のいびき外来もしています。)
子どもの歯の矯正はいつから?
子どもの歯の矯正はいつから始めるのが良いのでしょうか?
よく受ける質問のひとつです。私の子だったら小学校低学年からします。
気になり始めたら、まず歯医者さんに相談しましょう。それが、一番です。
もし、「様子を見ましょう」と言われたら、
できるなら、もう一軒別の歯医者さんにも相談しましょう。
歯医者さんによって、見方も違います。いろんな考え方があります。
幼児の定期健診・フッ素塗布をしている最中に「おや? 歯並び要注意だぞ! 」
と思うことがあります。
その内容をご家族の方に伝えると「まだまだ大丈夫」と考えていらっしゃるお母様の心には、この要注意信号は届きません。
でも「そうそう、前からちょっと気になっていたの」というお母さんは、こちらの話を熱心に聞いてくださるのです!
幼児の歯並びはお父さん・お母さんが「ちょっと気になるぞ」と思い始めた時期が、始める時期の一つでもあるのでしょう。まだ、子どもは小さいから大丈夫だと思っているうちに時間は、あっという間に過ぎてしまいます。子どもが大きくなるのは、本当に早いです。

☆☆☆顎の基礎を育てるのは成長期が一番!
顎の大きさや上下の前後関係の基礎を育成するのは、成長期が最適です。
大人になっても多少は改善できますが、難易度が違ってきます。
特に上下の前後関係がそうです(顎の大きさは成人になってもある程度改善できます)。
成長期に顎の基礎的な大きさや、上下顎の前後関係が適正に育っていることは後々、その子にとって大いなる財産になります。
勉強と同じですね。基礎はやはり成長期に身に付けるのが一番です。
「鉄は熱いうちに打て」、「少年老い易く学なりがたし」のとおりです。
特に受け口については画期的で簡単な道具が開発されています。
歯並びが悪いとどのような影響があるか
歯並びが悪いとどのような影響があるか、とのご質問をよく受けます。
歯並びが悪いと、まず、虫歯、歯周病になりやすく、成人に近づいてくると顎の関節の病気である顎関節病(通称:顎ズレ)になります。特に最近ではこの顎関節症が増えています。
顎関節症はいくつかの原因が重なることにより生じると認識していますが、 歯並びが悪いことはその一つの要因になります。また、良くないバランスのため、奥歯などを繰り返し悪くして歯を失う原因にもなります。
歯並びが悪くなる原因がそのままだと、、、
また、歯並びが悪くなる原因がそのままですと、成人以降、何度も虫歯治療を繰り返す部位が 偏ってきます。一般の方は「また、同じところの虫歯の治療・・・。この歯は何度も治療するわね・・・。」と単に何度も虫歯ができているとしか考えませんが、実はそれには深い理由があるのです。
なぜ悪くなるかという原因が分からないまま治療を繰り返し、歯を失ってから大原歯科に初めて来院されます。そして、歯のない部分を治療する際に「取り外し式の入れ歯にしますか?健康な歯を削ってブリッジにしますか?それともインプラントにしますか?」という話になってしまうのです。私は矯正治療のみならず一般治療を通じて、そのような患者さんを毎日のように診ています。
私は一般診療もしますので、歯並びの影響が、30歳台~40歳台以降にはっきりとした形で患者さんを困らせることをよく知っています。成長期の子どもはまだいろいろ柔軟だから、自覚症状が出にくいだけなのです。
早い人は20歳くらいでも自覚症状がでます。何度も同じ箇所の銀歯が繰り返しはずれ、そのたびに段々深い治療となっていき、やがて歯を失ったり、歯周病の形で歯を失ったり、顎関節症になったり、頭痛がしたり・・・、咬み合せの話は奥がとても深く、全部をここでは書き尽くせません。
川の上流、川の中流、川の下流で考えると、やはり川の上流から改善することが、歯と健康を根本から守ることには効果的です。
良いタイミングで、早め早めに予防するのが一番ですね。
いっき ちりょう・ にき ちりょうって何?
いっき ちりょう とは? にき ちりょう とは?
Ⅰ期治療とは? Ⅱ期治療とは?
Ⅰ期治療は まだ乳歯の残っているこどもの矯正のことです
Ⅱ期治療は 全部永久歯になった大人の矯正のことです
個人差はありますが、中学校くらいからがⅡ期治療になります。
自分で気付かない 「態癖(たいへき)」 ありますか?
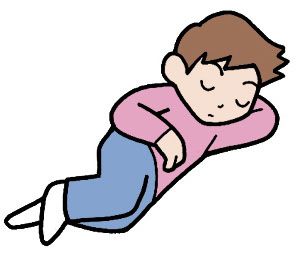
態癖とは、頬杖(ほおづえ)、うつ伏せ寝、横寝など日常なにげなくしている癖のことです。毎日している癖です。つまりポーズの癖です。
態癖により顎や口の周りに、歯や骨をゆがませるよけいな力が かかります。
それにより歯並びが悪くなったり、歯周病が進行したりします。
この癖は、総入れ歯やインプラント治療や歯周病にも関係しているのです。
ショルダーバッグを片方の肩にかけ続けても、最終的に噛み合わせがわるくなったり、歯並びがみだれたりという症状につながります。 自分では何気なくしていて、気付いていないことが多いのですが、誰しも態癖をもっているものです。
「なくて七癖 あって四八癖」ともいいます。そういうものです。
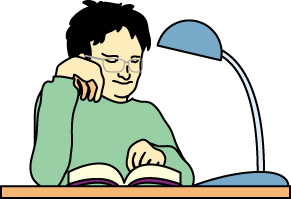
船がどこを目指しているのか?が大切

歯並びの治療を船に例えてみましょう。
ある船は普通の設備で普通のスピードで進み、正しい目的地に到着しました。
また別の船は豪華な設備でスピードが速くて、目的地到着までの期間は短いのですが、たどり着いた場所は本来の目的地ではありませんでした。
大原歯科では、その人その人が、今どんな状況かを 正確に診断することに全エネルギーを注ぎます。
例えば、上の前歯が出ているのが気になる人が来院したとします。
本人の思っているように本当に上の前歯が出ているのでしょうか?
以前、人間は地球の周りを太陽が回っていたと信じて疑いませんでした。
でも、本当は回っていたのは、太陽ではなくて地球だったのです。
それでは、なぜ、その人は上の前歯が出ているように見えたのでしょう。
正確に、歯についてその人の状態をひも解いていけば、「なーんだ。原因は当たり前のことばかりが重なってしまっているのですね。」って言われます。
根本から考え、地味に原因をひも解き、船をその人その人の正しい目的地に 到着させるのが大原歯科の方針です。
歯並びの形が良くなってからが本当の勝負なのです
歯ならびの形が良くなってからが本当の勝負です。
なぜ今までその形だったのかを精密に分析しておく必要があります。
また、元の歯ならびに戻っては何のために努力してきたのか、、ということになりかねません。
良い歯並びになるというのは、治るための一つの要素にすぎません。
良い形になるというのは、治っていくための土俵にようやく上った状態と思ってください。
その後の決め手、それからその歯ならびの形を維持していくのは、それ以外の要素をいかに努力するか、にかかっています。
横寝や頬杖などを気をつけたり、良く咬むことも大切ですが、それだけではないのです。
抽象的表現で分かりにくいかと思います。
ホームページではヒントしか伝えられないのが残念です。
必見!口の中が狭くなると、どういうことが起きるか、ご存知ですか?
口の中が狭くなると、どういうことが起きるのでしょうか。
まず、舌が収まるスペースが不足し、舌は気道を圧迫します。
気道を圧迫すると、呼吸が不足し、酸素不足になり、成長に大きく影響する可能性があります。
(この点、個人差があります。しかし、酸素不足の状態で成長させますか?酸素が足りた状態で成長させますか?)
このようなことが、大人になっていびきや睡眠時無呼吸症候群の原因になることがあります。
だから早く気づき必要な場合、治療する方が良いと思います。
態癖などで、お口の中が狭くなり、舌の居場所がなく、舌がしかたなく奥に押し込められ、舌が気道を圧迫すると苦しいので、猫背になってしまいます。そうするとダイナミックに悪い力バランスになり、歯並びがさらに悪くなります。
直立二足歩行と理想的な歯並びについて(足育について)
80歳になってもズラッと歯がきれいに並んで、「わしゃ、歯医者に行ったことなど一度もない。でも歯は全部 丈夫じゃ。わっはっはっは。」というおじいちゃんが、稀にいらっしゃいますよね。
私の経験の中では、そういう方は決まって、若いころから楽をしておらず、しっかり歩き、しっかり体を動かして働いてきている人です。
人間にとって健康的で良い歯並びとは、「直立二足歩行に適応した歯並び」とも言えると考えています。
何万・何十万年もの進化とともに直立二足歩行を確立し、それとともに直立二足歩行に適応した歯並びになった。そして、文明の発達とともに、直立二足歩行の機会が少なくなっていき、歯並び含めて体のあちこちが型崩れをしてきた(退化してきた)とも言えます。
小さい頃からの足育が大切なのです。
食育など他の要因も重なっています。