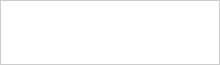小児の治療
大原歯科・矯正歯科では、子供を押さえつけて治療しません。
大原歯科では子供を押さえつけて治療しません。
私は多くの大人の患者さんも診てきましたが、子供の頃、無理に押さえつけられて治療した経験をお持ちの方は、歯科治療にとても恐怖心を持つため、虫歯になっていると自分で分かっていても怖くて歯医者さんに行けずに、いよいよ市販の痛み止め薬が効かなるまで放置されていることが少なくありません。最も良い道は、子供の頃に虫歯がひどくならないようにコントロールすることです。
(例外的に、ケガで歯を打って来院された子を、バスタオルなどで体を巻いて治療する場合があります。幼稚園や小学校が近いため、ケガで歯を打って来院される子も結構います。)
子どもが歯みがきを嫌がって泣く時どうすれば良いか?
子どもが歯みがきを嫌がって泣いたら、どうしますか?
うちの子供も、2~3才の頃は、朝・昼・夜の3回の歯みがきをとても嫌がりました。
母親が子どもを横にねかせて、子どもの足を母親の足で包み込んで押さえつけるようにして磨いている時期もありました。磨いている間は、ずっと泣いていました。少し、かわいそうかな、とも思いできるだけ短い時間ですませてしまおうと考えることもありました。手抜きですね。
いつか、泣かずにみがくことが出来るようになるのか?
歯みがきが大嫌いな小学生になってしまうのか?
など悩んだこともあります。
それが、なんと4才頃、泣かずに我慢ができるようになったのです。
口の中に、歯ブラシを入れてもその不快さに少し慣れたんでしょうか?
不思議ですね、だんだん出来るようになるのではなくて、いきなり突然泣かなくなるんですね。
少しずつ歯みがきの大切さを話し、虫歯の怖さも教え、それがようやく伝わったのかなと、とても嬉しかったです。磨き残して虫歯をつくるよりも、頑張ってみがいていれば、いつかそれが子どもの心に届くのではないかと思います。自分一人で歯磨きができるようになるには、まだまだですが、これからの成長を見守りたいと思います。もちろん、フッ素を塗ることも大事ですね。
3の倍数で変化していく子ども達
1歳半健診、3歳児健診、6歳で小学校入学、9歳で小学校の中心である3,4年生に、12歳で中学に入学、15歳で・・・、18歳で・・・、というふうに子ども達は、大まかに
3の倍数で心身と頭脳が変わっていきます。
(6歳の時に6歳永久歯が生え、その後ろの7番目の歯が12歳で生え、そのまた後ろの8番目の歯(親知らず)がおおよそ18歳で生えてきます・・・。なんだか神秘的ですね。)
まっすぐな坂を上るのではなく、らせん階段を1歩1歩上るように大人へ近づいていきます。
大事なのは、らせん階段の上部の行き先はあらかじめ決まっているのではなく、その子その子が日々をどのように過ごすかによって、目の前に出現する次の階段が異なり、階段の行き先が変わるということです。
6歳になって今までできなかったことが急にできるようになったり、小学校3、4年生にガラッとお子さんが変化し、言うことを聞かなくなったということを、すでにご経験をされた親御さんもいらっしゃることでしょう。
精神的な成長も勉強も運動も歯科治療も、この3の倍数の法則(?)を重視して取り組むと良いと思っています。
また、素直な人は良い指導者にめぐり合えれば、いくつになっても どこまでも成長するものだな、とも思います。
お子さんなどがケガで歯を打ったら、どうすれば良いか。
お子さんが転んだり、ぶつかったりして歯を打った場合、できれば早めに歯科医院に診てもらってください。
見てもらって大丈夫であれば心配することも減りますね。
歯がぐらついていたり、欠けたり、状態は様々です。
軽症の場合は消毒薬を塗るだけで済むこともありますが、状態によっては、 ダメージを受けた歯を両隣のじょうぶな歯と一緒に一時的な接着樹脂で固定しておいた方がよい場合もあります。
この一時的な固定は、基本的には約1ヶ月ではずしますが、状態によっては1ヶ月以上固定する場合もあります。
大原歯科では今まで1~3ヶ月ではずしています。
どんなケガでも初期段階で、正しい手当てを受けるかどうかで、治りが左右されます。
歯医者さんにはどんなふうに歯を打ったのかを具体的に説明した方がよいです。
また、緊急に抗生剤も処方することが多いため、お子さんに薬アレルギーがないかどうか小学校や幼稚園、保育園に事前に知らせておいた方がよいでしょう。
多くの歯科医院は予約制なので、外傷の急患さんが来られた際は、他の予約の患者さんの治療中で、すぐには診れない場合もあります。
大原歯科でも同じ状態で、前後の患者さんにお願いして少しずつ時間をいただき、対処することもありますが、中にはどうしても時間が作れなくて、 他の歯科医院に電話して診ていただくこともあります。
いずれにしても早い的確な処置が必要であるため、ともかくケガで歯を打ったらすぐに歯医院さんに電話した方がよいでしょう。
スポーツや外遊びをよくする子はスポーツ用マウスピースを持っておいた方が安心ですね。
私の経験では、幼稚園の年中さんや小学2年生が、外傷によって歯を打つことが多いです。
幼稚園や小学校に慣れてくる頃が、最もケガをしやすいということでしょう。
小学校では3年生前後になると自転車で転んで、歯を打つ子がいます。
今まで外傷で診てきた子の中で、自転車で転んだ子は皆、歯が折れていました。
このように自転車のエネルギーはあなどれません。
また万が一、ケガの勢いで、歯が抜けてしまった場合は「汚れを落とさず」、抜けた歯を牛乳につけた状態か、もしくは抜けた歯をお母様などのベロ(舌)の下に置くか、薬局で「生理食塩水」を購入して、清潔な容器に生理食塩水と抜けた歯を入れて、歯医者さんに持って行ってください。
うまくいけば歯が再度くっつくことがあります。
汚れをキレイに落としてしまうと、その刺激で根の周りの「歯根膜」という大事な膜を 傷つけてしまって、歯がもうくっつかなってしまうことがあるため、抜けた歯に汚れがついていてもあまりゴシゴシしないでください。
虫歯の再発はゼロです☆!☆(開業以来今まで10年間)
子供の治療だけでなく、大人の治療でも同じなのですが、開業して以来今まで(平成13年~平成23年の10年間)、定期健診を受診されている方の虫歯の再発はゼロです。
私が治療した詰め物の下には虫歯が再発していません。私としては当たり前のことを当たり前にしただけなのですが。プロとして、複数の基本のポイントを踏まえてキチッと治療した結果です。
21世紀です。もう虫歯の時代じゃないんです!! の記事も見てね
虫歯にならないために
 かつて天然痘が世界中の人々を苦しめた時代があります。
かつて天然痘が世界中の人々を苦しめた時代があります。
しかし、人間の英知により撲滅することができました。
同じようにかつて「虫歯の洪水」という言葉で表現されるような時代がありました。 昨今の日本では喜ばしいことに、虫歯をかなり減らすことができるようになりました。
これは予防技術の進歩(虫歯発生機序の解明、フッ素の応用など)と、皆さんの努力により達成できたすばらしいことであると思います。 今は予防すれば、虫歯を作らずに済む時代です。
おおはら歯科では患者さんの知識を少しずつ高め、生活習慣改善その他の情報を少しずつ提供します。
必要なことを実践される患者さんは、虫歯がほとんどできません。
「虫歯がほとんどない」というのが、当たり前の時代になりました。
歯磨きだけでは、虫歯は防げません!
「歯磨きしているから、安心」ではありません。
歯磨きだけでは虫歯は防げないのです。
フッ素の応用の他にも、おやつのとり方、飲み物の種類、その後のケアの仕方、お母様が知って実践することはたくさんあります。
お子さんにとって本当に良いプレゼントとは何でしょう?
今、ある大学生が来院されています。
その方は
「私は子どもの頃、食について親の躾けが厳しく、甘いおかしを食べさせてもらえなかった。」
と不満げに言います。
でも、この方の歯と歯の間には全く虫歯がありません。
私は「甘いおかしを与えられなかったことが、あなたにとって親御さんからの最高のプレゼントだったのですよ。おかげで歯と歯の間に全く虫歯がないじゃないですか。」
学生さんは、「なーるほど~。」と頷きました。
甘い物が絶対にダメというわけではありませんが、上記の話は「お子さんにとって、何が本当のプレゼントになのか」を考えさせられます。
参考までに書きますと、2歳までに味覚の神経がほぼ完成するので、その時期までに甘味、濃い味に慣れてしまったら、その後大変な目に遭うのはお子さんです。
兄弟・姉妹では下の子ほどその環境にありますので、注意しましょう。
また、「3時にオヤツ」と決めていた場合、例えば2時50分にオヤツが欲しいとダダをこねられたので、お子さんに与えてしまうと、自制心の育成の面で心配です。
「2時50分から残りわずか10分間、がまんできるかどうか」・・・たったこれだけで、その後に大きく差が出ることでしょう。
ハレの日、ケの日
昔は、ハレの日とケの日がはっきりしていました。
普通の日であるケの日では、ケーキなどは食べませんでした。
誕生日など、晴れ着を着てお祝いをするハレの日には、ケーキなど普段食べることができないごちそうを食べることができました。
普段食べることができないから、ハレの日に食べるケーキは、通常の何倍もおいしくて、うれしいものでした。
今はどうでしょう。
毎日がハレの日の食事になっていないでしょうか。
不便だった昔の人と、今の人とどちらが、健康で幸せでしょう?
酸蝕歯(さんしょくし)って何?
虫歯菌が原因で歯が溶けるのが「ムシバ」ですが、虫歯菌が原因ではなく身近なすっぱい食べ物や飲み物で歯が溶けた状態のことを「酸蝕歯」といいます。
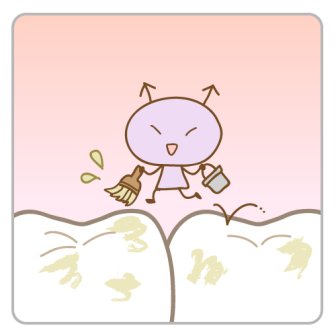
例えばレモンはpH(ペーハー)が2.1ですが、飲んだらスカッとする炭酸飲料はpH=2.2です。レモンとほとんど同じくらいの酸なのですが、砂糖の甘みのため、あまりすっぱさを感じないようになっています。その炭酸飲料に抜いた歯を漬け込んでおくと、1時間後には歯の表面はボコボコになります。
それほどすさまじい「酸」なのです。
pH=5.5より低い値のすっぱさから、歯のエナメル質は溶け始めます。
その他、栄養ドリンクでは種類によりますがpH=2.5くらい、
スポーツ飲料ではpH=3.5~3.8、
飲むタイプの野菜ジュースではpH=3.9、飲むタイプのヨーグルトではpH=4.1・・・などなど
これらの飲料が悪いわけではなく、大切なのはこれらを摂取の方法と摂取後のケアの知識を知り、実践することです。すっぱいものでも体に良いものもありますから、歯のケアを知ればよいのです。
でも、炭酸飲料なんて小さい子の歯にはもっての他。
お子さんには酸性の飲み物をダラダラ飲みさせないでください。
特に眠る前にはあまり飲ませたくないところです。
麦茶などで中和できますので、歯磨きがまだ難しければ、眠る前はせめて麦茶を飲ませた方がよいです。
小さい子が病気の時はそうも言ってられない時もあるでしょうが、なるべくすっぱい口の中を作らない方がよいです。
この酸蝕歯の状態にさらに、磨き残しがあると・・・・、ぞっとします。
歯磨きの仕方ですが、すっぱい物を摂取した後、水やお茶を飲んでください。
それから30分も経つと唾の力で歯がやわらかくなるのが抑えられますので、それから歯を磨きましょう。
すっぱい物を食べたり飲んだりした直後は、歯の表面がやわらくなってしまっていますので、その時点でゴシゴシしたら、エナメル質表面がはがれてしまいますので注意が必要です。
シャボン玉EMせっけんハミガキについて
(シャボン玉EMせっけんハミガキ)
ほとんどの歯磨き粉には合成界面活性剤が入っています。
合成界面活性剤は体に良くないです。
シャボン玉EMせっけんハミガキには、合成界面活性剤が入っていません。
シャボン玉EMせっけんハミガキを使用している私の個人的な感想ですが、善玉菌を増やして悪玉菌を減らしているのでは?という直感を得ます(科学的な証明はまだ私はしていません)。善玉菌が増えれば、悪玉菌である虫歯菌や歯周病菌が減るはずです。
合成界面活性剤であるラウリル硫酸ナトリウムについてのサイト
https://www.yogoreotoshi.com/post-0-4/
石油系合成界面活性剤について次のサイトをご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=GivoUuADpCs&t=6s
シャボン玉EMせっけんハミガキについては次のサイトをご覧ください。
子供のフッ素について
歯科医院で使うフッ素には、【フッ化ナトリウム】と【フッ化ジアミン銀】の2種類があります。
【フッ化ナトリウム】の活用について、現在 私は消極的です。
もう一つの【フッ化ジアミン銀】については、その効果を日頃の診療で目の当たりにしています。そのため虫歯治療においては患者さんの同意を得た上で、フッ化ジアミン銀をよく活用しています。
この2種類を、ひとくくりにし「フッ素」と表現することが多いのですが、2種類を同一の扱いをしていろいろな記事に書かれてあるのが残念でなりません。
フッ化ジアミン銀は、上手に使えばメリットがデメリットを上回ると日々診療で実感しています。
フッ化物を使う場合は「なるべく飲み込まないでください、できれば絶対に飲み込んでほしくない。」と患者さんに伝えて、歯に塗布した後うがいをしてもらいます。
私自身の歯にも(虫歯になったら大変なため)フッ化ジアミン銀をよく塗ります。
その後しっかりうがいをします。
フッ化ジアミン銀は、徳島大学名誉教授 西野瑞穗先生が京都大学大学院生の時に開発なさいました。(商品名サホライド;40~50年前くらいに日本メーカーが商品化し販売しています。)
下記の西野先生関連のホームページサイトもご参考になってください。
https://www.icd-japan.gr.jp/pub/vol48/07-vol48.pdf
https://sweden-kokufu.net/blog/item.cgi?Id=5
「重曹うがい」は素晴らしい。
フッ素は確かに歯を強くしますので、大原歯科ではフッ素も応用するのですが、体のためには、フッ素はあまり飲み込まない方が良いです。
何でもかんでも塗りたくるのは良くないと思います。
フッ素は適量に使ってこそ、メリットがデメリットを上回ります。
最近では、大原歯科では「重曹うがい」を皆さんにお勧めしています。
食育について
私は栄養学の専門科ではありませんが、医療者として様々な患者さんの治療をする際に、1歳前後の子から高齢の方まで、必ず「毎日 何を食べているか。」の話題をします。なぜなら、まず、食生活は真っ先に歯や歯並びに直結しますし、体や健康は日々の食べ物から成り立ち、歯医者といえども糖尿病やリウマチ、高血圧などのお年寄りの健康状態に注意しながら治療をしますから。
僭越ながら食事に関する私見を述べさせていただきますと、私は経験的に次のように考えています。
食事において例えば1900年のような昔には存在しなかったような成分をなるべく体の中に入れない方が良いと思います。
あくまでも私の主観です。ご参考までに。
口腔機能発達不全症とは何ですか?
日本の子ども達の中で、ロウソクの火を吹き消すことができない子ども、口笛を吹けない子どもが増えています。
咬合を育成する上で、それ以前にその子達が生きていく上でとても由々しき事態だと考えます。
果たして日本の子ども達がこれからの社会を生き抜いていけるのだろうかと心配です。
大人達が何とかしないといけないと感じます。
食にまつわる今の社会の問題点がこの本に書かれています。
是非ご一読を。
新装:食卓の向こう側コミック編が発売 これが食育・息育の決定版 – 福岡のみらいクリニック
お子さんがいらっしゃるほとんどの皆さんにとって、
口腔機能発達不全症という言葉は、たぶんあまり聞きなれないと思います。
口腔機能発達不全症は、子ども達における新たな病気です。
これは、乳児期の授乳の方法や、離乳食の方法、食べる時の姿勢、いつもの生活におけるお子さんの遊び方など、いろんな要因が複合して生じる可能性があります。
3つの予防方法
最近ではお子さんの虫歯の数は減少している一方で、不正咬合は約6割以上にも増えていると言われ、年々増加しています。
お子さんの歯並びの乱れやバランスの良くない咬み合せは、口腔機能発達不全症と深い関係があります。
口腔機能発達不全症を放置すれば、次のようなトラブルの恐れがあります。
気を付けないといけないのは、成長後(13~15歳以降)の改善する見込みがないので、「虫歯」や「歯周病」と同様に「歯並び」の予防も大切ということになります。
大原歯科では、新たな病気である口腔機能発達不全症を予防するということに力を入れ、お子さんと親御さんに対して多様な情報提供をしています。
口腔機能発達不全症は、実際どういう事が起きるか。
- 顎の成長不足で、顔が上下に長くなる。
- 顎が十分に大きくならないことで、歯並びや咬み合せが悪くなる。
- 顎の成長不足により、空気の通り道である鼻腔や気道が狭くなり、呼吸が難しくなる。
お子さんの口腔機能発達不全症をチェックしてみましょう。
お口元の役割には、生きていく上で絶対に必要な「食べる」や「呼吸する」という働きがあります。
さらに、「話す」、「表情を作る」という社会で生きていく上で必要なコミュニケーションにも非常に深く関わります。
元々、私達人間は個人個人にとってそれなりに正しいとされる歯並びになるようにできているはずです。それにブレーキをかける要因(お口周囲の悪い癖)が多くなることで、「食べる」「呼吸する」「話す」「表情を作る」にトラブルが生じるとされています。
元々の骨格的要因などを全く否定するわけではありませんが、口腔機能発達不全症はその多くが早期のトレーニングやプレオルソという道具などによる治療により改善・解消が可能だと言われます。
実際に多くの子達の歯並びや口腔機能が改善されています。
次のような症状に心当たりはありませんか?
口腔機能発達不全症のチェックポイント
(食事について)
□ 食べ物がしっかり噛むことができない。
□ 飲み物や食べ物をうまく飲み込めない。
□ 食べこぼしがよくある。
□ 食事中にむせることがよくある。
□ 食事が極端に早い、あるいは極端に遅い。
□ 食事の時に、クチャクチャと音を立てて食べる。
□ 口の中にいっぱい食べ物を詰め込んで食べる。
□ 乳児の場合、ちゃんと授乳できない。
(発音について)
□ 口を閉じることが難しく、パ行が発音しにくい。
□ 舌が上手に動かずに、カ行、サ行、タ行、ラ行をうまく発音できない。
□ 滑舌が良くない。
(いびき・顔面の変形・猫背など)
□ いびきがある。
□ 肥満である。
□ 顎の形の変形
□ 顔の前後が短くなり、上下が長くなっている。
(その他)
□ お口がポカンと開いている。
□ 鼻呼吸ではなく、口呼吸をしている。
□ 歯並びが良くない。
□ 離す時に唾が口の横にたまる。
□ 舌が短くて、アッカンベーと舌を突き出した時に先端がくぼむ(極端な場合、ハート型になる)。
□ 口を閉じた時に顎の先が梅干し状態になる。
□ 唇にぐっと力が入る。
□ 笑う時に頬がふっくら盛り上がらない。
□ 口角が上がらない。
□ 唇が厚ぼったい。
□ 顔の血色が良くない。
□ 目に力がない。目の下にクマがある。
□ 表情が暗い。健康的でない。
どれか一つでも該当したら、口腔機能発達不全である可能性があります。
これらの症状は、お子さんが実はお口を上手に使えていないことが原因であることが多いのです。
最近では、こういったお子さんが増え、同時に口腔機能発達不全症と深く関わる歯並びの悪いお子さんが増えてきているのです。
個人的には30年前とはずいぶんお子さん達の様子が変わってきていると感じます。
口を使って人はご飯を食べる・・・
昔では当前の事ですが、この当前の事が現在の生活において自然に学習されていますでしょうか?
ほとんどの皆さんが自然に身につくとお考えかと思いますが、この昔では当たり前だったことが、今や自然に身に付かないことが、少なくないのです。(涙)
このようなお口を使う方法は、乳幼児期における哺乳、離乳食の時期、それから通常の食事へ、というふうに段階的に少しずつ、学習するものです。
しかしながら、それぞれの時期における食事の方法が、昔とはずいぶん変化しており、昔本来ならば、普通に学習できていた良好なお口の使い方が、獲得できないまま、お子さんが大きくなっていしまっていることもあるのです。
このように上手にお口を使うことができない症状が口腔機能発達不全症と名づけられ、2018年度から新しい病気として認められ、保険治療の対象となった経緯(いきさつ)があるのです。
早期に取り組む事のメリット
少年老いやすく学なりがたし・・・というコトワザがあります。
早い時期に口腔機能発達不全という病気を知り、少しでもできることをすることで次のようなメリットがあります。
- 何でも良好に咀嚼することができる綺麗な歯並びになる。
- 病気にかかりにくくなり、健康で正しい成長が促進される。
- より顔立ちが良好になり。
口腔機能発達不全症によりどのような悪影響があるか
口腔機能発達不全症を放置してしまって何もしなかった場合、下記のような悪影響が長期的に起きるリスクがあるとされています。
そして、注意しなければならいことは、そのように成長した後は、幼少期に比べて改善しづらくなり、改善するのにもかなりの労力が必要となるということです。
根本的な問題が解決されなかった場合、成長後(主に15歳以降)にいくら矯正をして歯並びを改善させたとしても、元の悪い歯並びに戻ってしまうことまであり得るのです。(涙)
①歯並びが乱れ、咬合バランスが悪くなる。
本来ならば、私達の上と下のアゴ(顎骨)は、お口周りの筋肉の適正なバランスや咀嚼を繰り返すことで加えられる適正な力によえう刺激によって、健康的に成長します。
口腔機能発達不全症では、アゴに適度な刺激が加わらず、適切な成長を促さないリスクがあります。そして顎が小さいままとなり、歯並びが悪くなるということに陥るのです。
②口腔機能発達不全により本来の自然な鼻呼吸が困難になる。
上あご(上顎)への適切な刺激が不足することにより、健康的な呼吸にとって本当に重要な空気の通り道である鼻腔と気道が狭くなり、本来の自然な鼻呼吸がしにくくなり、口呼吸が多くなります。
③姿勢が悪くなる。
鼻腔・気道が狭くなると、無意識に気道を拡げるために猫背になり、口呼吸をするようになってしまいます。猫背は首・肩・背中・腰に過剰な負担をかけそのまま成長期を過ごし、成人となり、 年齢を重ねていきます。
④顔が縦に長く見えるようになる。
顎が前方的・側方的に成長不足になると顔の適度な膨らみが得られず、上下に長くなっていきます。
口腔機能発達不全症は何もしなければ、次のような症状を増悪させてしまいます。
例えが適切でないかもしれませんが、丸っこく育つはずのトマトを三角の容器に入れて育てると三角のトマトになります。いったん三角になったトマトを元々の形である丸いトマトに戻すことはかなり困難でしょう。(涙)
まだ形が三角になってしまわないうちに柔軟性があるトマトを自然に戻し、本来の形に促すことが、とても重要であることがお分かりになっていただけると思います。
骨格的な異常はこの時期に治療することがとても効果的で、成長後に悔やんでも骨格的な異常を治すには、現時点での治療技術では外科手術が必要となります。(成長後の骨格の異常は、歯の移動のみの矯正治療では改善ができません。)
鼻呼吸できずに呼吸となり、さらに気道が狭く呼吸が苦しく慢性的な酸素不足になれば、集中力が低下し、姿勢が悪くなり、将来多くの禍根を残すことにもなりかねません。病気の原因になったり、勉強・仕事に悪影響を与え続ける可能性があります。
さらにお子さんが高齢者になる前後において、自分の力で食事をすることが難しくなる口腔機能低下症になる危険性が高まります。
小児の口腔機能発達不全症の放置は一生にわたって悪影響を及ぼす意味合いがあるということです。
(口腔機能発達不全症の対策・予防矯正処置)
予防矯正治療は、歯並びが悪くなる根本原因である舌の位置や動かし方や口腔周囲筋の力バランスの改善を図り、よりキレイな歯並び、お子さんのより良いお顔立ち、より健康的な成長を促進する治療です。
お口・顎の適切な発育と良い歯並びは、お子さまの健康的な成長にとってとても大切です。お口周囲の悪い癖があれば歯並びも悪くなります。
さらに虫歯や歯周病になりやすくなり、成長後に働き盛りやお年寄りになった時に歯を多く失ってしまう危険性が高まります。
さらに、風邪を引くやすくなるなど病弱になり、全身にまで影響を及ぼすことが知られるようになりました。
大原歯科では、お子さまの口から全身に関係する健やかな成長について、皆様にいつも情報提供をしています。